「第18回東京-北京フォーラム」における大使挨拶(2022年12月8日)
令和4年12月8日

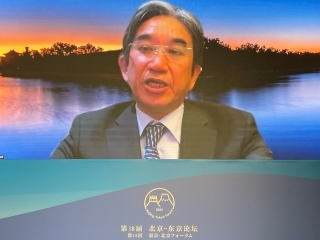

12月7‐8日、言論NPOと中国外文局が主催する「第18回東京-北京フォーラム」が東京と北京の会場をオンラインで結んで開催され、「世界の平和と国際協調の修復に向けた日中両国の責任‐日中国交正常化50周年で考える‐」をメインテーマに、両国の政府代表や有識者の間で活発な議論が行われました。
垂秀夫在中国日本国大使は、12月8日の全体会議において挨拶を行ったところ、挨拶全文は以下のとおりです。
会場にご来席の皆様、オンラインでご参加の皆様、こんにちは。
コロナ禍において日中間の往来がいまだ難しい中、日中双方の関係者の御尽力により、第18回「東京-北京フォーラム」が成功裏に開催されましたことをお喜び申し上げます。
この2日間、両国を代表する有識者の間で、様々なテーマについて忌憚のない議論が重ねられたと承知しています。共通認識に達したものもあれば、立場の違いが際立ったものもあったかと思います。
私は、体制の異なる隣国同士、立場や意見の違いがあるのはごく自然なことであり、むしろ我々が心配すべきは、対話や交流がなくなることであると常々申し上げております。その意味において、日中関係の現状及び未来をこうして語り合うことは極めて重要であり、高く評価したいと思います。
日中国交正常化50周年の本年も、残すところ3週間余りとなりました。紆余曲折を経てきた日中関係ですが、「50周年」の本年11月に、バンコクで日中首脳会談が開かれたのは非常に良かったと思います。
岸田政権が掲げる対中政策は、「建設的かつ安定的な日中関係の構築」でありますが、その意味するところは、互いに主張すべきは主張しつつも、率直な対話を重ね、共通の諸課題について協力していくというものであります。
これまで、ともすれば「主張すべきは主張する」という部分のみにフォーカスされがちでしたが、今回の首脳会談において、首脳間で少なからずの共通認識を達成し、日中間でいかに「建設的な関係」を構築していくかが明確になったことが一番の成果であったと考えています。
しかしながら、今回の首脳会談の開催によって、日中間に横たわる課題が一変したわけではありません。尖閣諸島の問題では、先月でも3回もの領海侵入が発生しています。また、日本の近海では、国際法を公然と違反し、ウクライナを侵略している国であるロシアと共同で中国は爆撃機を飛ばし、軍事訓練を行っています。こうした行為が続くようでは、国民感情が容易に改善しないことは「火を見るよりも明らか」(洞若观火)でしょう。
そうした意味では、今後とも日中関係の舵取りはますます難しくなっていくことが予想され、本格的な関係改善に向けたプロセスは、これからが「本番」と言えます。
こうした中で、日中両国に求められることは、あらゆるレベルで意思疎通を積み重ねていくことに尽きると考えています。とりわけ、首脳間で頻繁な意思疎通を重ね、政治的相互信頼の基盤を固めていくことが何よりも重要であります。中国側から招請を受けている林芳正・外務大臣の訪中も、早期に実現していく必要があります。
また、首脳会談では、国民交流の再活性化についても合意がありました。日本は水際対策措置を全面的に緩和しましたが、今後、日中間の国民レベルでの相互理解や経済往来を深めていくためには、中国側の水際対策措置が早期に緩和されることを期待してやみません。
こうしたことを考えていくと、日中関係改善の道のりは、常に「任重くして道遠し」(任重而道远)の繰り返しであります。
御来席の皆様、
本年は日中国交正常化50周年ということもあり、本日は、日中関係の歴史について少し愚見を述べさせていただきたいと存じます。ただし、私が申し上げる歴史は、必ずしも50年に留まるものではありません。
私は、外交官であるとともに、ひとりの風景写真家でもあります。大使として赴任してからも、カメラのレンズを通して、中国の美しい風景を数多く切り取ってきました。
私が足しげく通う撮影スポットの一つに、北京植物園があります。北京市北西部に広がる広大な敷地を擁する北京植物園を訪れる度に、四季折々の自然の美しさを感じることができます。とりわけ、梅、桃、海棠、チューリップなどが咲き誇る春の美しさは、安直な言葉では表現しきれないほどであります。その北京植物園の北東側の静かな一画に、数奇な運命をたどった梁啓超が家族と共に眠っています。
梁啓超は、私から説明するまでもなく、清末・民初に活躍した、中国近代史を代表する思想家・政治家・ジャーナリストであります。1895年、当時22歳の梁啓超は、師と仰ぐ康有為と共に科挙の試験を受けるため上京した際、日清戦争の敗北により締結した下関条約の内容を知って憤慨します。
日本の明治維新にならった政治体制の変革・近代化が必要であると強く認識した彼らは、光緒帝の下で立憲君主制の樹立を目指し、1898年に「戊戌の変法」と呼ばれる改革を推進しました。
しかしながら、その後、西太后・袁世凱らによるクーデター、いわゆる「戊戌の政変」により、100日余りで改革はつぶされ、梁啓超ら「変法派」は弾圧されました。この政変により、仲間の多くが刑死する中、梁啓超は日本に亡命し、その後、辛亥革命の翌年に当たる1912年まで、つまり25歳から39歳までの14年間を日本で過ごしました。ちなみに、同志の康有為もまた、香港経由で日本に亡命しています。
さて、日本滞在中、梁啓超は、「清議報」、「新民叢報」といった雑誌や新聞を創刊するなど、様々な媒体を通じ、日本語に翻訳された西洋の新しい思想や文化を中国国内にもたらしました。彼は、思想面での変遷が指摘されることはありますが、中国の近代における国民思想の確立に果たしたその歴史的役割は大きく、また、近代中国最大のジャーナリストとして、当時の青年知識人に与えた影響は絶大であったと言えるでしょう。
ではなぜ、そのような啓蒙活動が円滑に実現できたのでしょうか。それは、当時梁啓超が、日本で創られた新たな漢字、いわゆる「和製漢語」を積極的に受容し、使用したからであります。当時の日本では、明治維新を経て、西洋文明を積極的に吸収する中で、漢字を新たに組み合わせることにより、西洋の概念を的確に翻訳し、多くの新たな単語が産み出されていました。
つまり、約1,600年前に中国から日本に伝来した漢字は、近代化の中で「和製漢語」として独特の発展を遂げたということであります。そして、梁啓超が西洋の新しい思想を中国に紹介していく過程において、その「和製漢語」は中国に「逆輸入」されることになりました。梁啓超だけではありません。清末の中国は、1905年に科挙が廃止されたことも相まって、空前の日本留学ブームが到来し、中国人留学生の数は、年間2万人にも上ったとされています。
そうした梁啓超や中国人留学生らの活動により中国にもたらされた語彙として、例えば、「世界」、「社会」、「経済」、「科学」、「革命」、「共産党」、「社会主義」、「幹部」、「独立」、「平等」、「自由」、「民主」など、枚挙にいとまがありません。現代中国語の中で、社会科学関連語彙の約7割が「和製漢語」であると言われていますが、そのお陰で、現在、日中間の意思疎通が極めて円滑になっていることは言うまでもありません。この二日間の議論でも、こうした用語が日中双方の有識者の間で幾度も使用されたことでしょう。
かつて中国から学んだ漢字を使い、日本は、その後の政治、経済、科学、文化、思想等、あらゆる面で国を発展させてきました。そして、近代に入り、今度は日本で創られた「和製漢語」で、日本が中国の近代化に寄与することになる、こうした漢字をめぐる日中関係の歴史は、まさに助け合いや学び合い、中国語で言えば「守望相助」の歴史の象徴であります。そうした意味では、梁啓超は、その歴史の過程において極めて重要な役割を果たしたとも言えるでしょう。
本年6月、私は、青島を訪れました。ある日、洋館が並ぶ静寂な坂道を散歩していると、康有為が晩年を過ごした旧居を偶然に見つけました。康有為は、日本滞在中に歳の離れた日本人女性を見初め、4人目の妻としました。二人が青島で共に暮らしたのは数年でしたが、私は、康有為の旧居の窓から青島の青い海を見ながら、その同志・梁啓超に思いを馳せ、そして、漢字が取り持つ不思議な日中両国の「縁」について静かに感じ入りました。
こうした「守望相助」(助け合い)の歴史は、漢字にまつわるものだけに留まりません。これまで日中間では、たくさんの助け合いのドラマが織りなされ、日中関係の歴史を形作ってきました。
日中両国は、引っ越しのできない隣国であり、いわば「永遠の隣人」であります。国交正常化50周年がまもなく終わろうとしていますが、我々はこの機会に今一度、日中関係は世界でもまれに見る「守望相助」(助け合い)の、二国間関係の歴史であることに目を向ける必要があるのではないでしょうか。
最後になりますが、御在席の皆様方の御健勝及び日中関係の更なる発展を祈念するとともに、今次フォーラムの開催に関わられた関係者の御尽力に改めて敬意を表し、私の挨拶とさせていただきます。
御清聴、ありがとうございました。
垂秀夫在中国日本国大使は、12月8日の全体会議において挨拶を行ったところ、挨拶全文は以下のとおりです。
会場にご来席の皆様、オンラインでご参加の皆様、こんにちは。
コロナ禍において日中間の往来がいまだ難しい中、日中双方の関係者の御尽力により、第18回「東京-北京フォーラム」が成功裏に開催されましたことをお喜び申し上げます。
この2日間、両国を代表する有識者の間で、様々なテーマについて忌憚のない議論が重ねられたと承知しています。共通認識に達したものもあれば、立場の違いが際立ったものもあったかと思います。
私は、体制の異なる隣国同士、立場や意見の違いがあるのはごく自然なことであり、むしろ我々が心配すべきは、対話や交流がなくなることであると常々申し上げております。その意味において、日中関係の現状及び未来をこうして語り合うことは極めて重要であり、高く評価したいと思います。
日中国交正常化50周年の本年も、残すところ3週間余りとなりました。紆余曲折を経てきた日中関係ですが、「50周年」の本年11月に、バンコクで日中首脳会談が開かれたのは非常に良かったと思います。
岸田政権が掲げる対中政策は、「建設的かつ安定的な日中関係の構築」でありますが、その意味するところは、互いに主張すべきは主張しつつも、率直な対話を重ね、共通の諸課題について協力していくというものであります。
これまで、ともすれば「主張すべきは主張する」という部分のみにフォーカスされがちでしたが、今回の首脳会談において、首脳間で少なからずの共通認識を達成し、日中間でいかに「建設的な関係」を構築していくかが明確になったことが一番の成果であったと考えています。
しかしながら、今回の首脳会談の開催によって、日中間に横たわる課題が一変したわけではありません。尖閣諸島の問題では、先月でも3回もの領海侵入が発生しています。また、日本の近海では、国際法を公然と違反し、ウクライナを侵略している国であるロシアと共同で中国は爆撃機を飛ばし、軍事訓練を行っています。こうした行為が続くようでは、国民感情が容易に改善しないことは「火を見るよりも明らか」(洞若观火)でしょう。
そうした意味では、今後とも日中関係の舵取りはますます難しくなっていくことが予想され、本格的な関係改善に向けたプロセスは、これからが「本番」と言えます。
こうした中で、日中両国に求められることは、あらゆるレベルで意思疎通を積み重ねていくことに尽きると考えています。とりわけ、首脳間で頻繁な意思疎通を重ね、政治的相互信頼の基盤を固めていくことが何よりも重要であります。中国側から招請を受けている林芳正・外務大臣の訪中も、早期に実現していく必要があります。
また、首脳会談では、国民交流の再活性化についても合意がありました。日本は水際対策措置を全面的に緩和しましたが、今後、日中間の国民レベルでの相互理解や経済往来を深めていくためには、中国側の水際対策措置が早期に緩和されることを期待してやみません。
こうしたことを考えていくと、日中関係改善の道のりは、常に「任重くして道遠し」(任重而道远)の繰り返しであります。
御来席の皆様、
本年は日中国交正常化50周年ということもあり、本日は、日中関係の歴史について少し愚見を述べさせていただきたいと存じます。ただし、私が申し上げる歴史は、必ずしも50年に留まるものではありません。
私は、外交官であるとともに、ひとりの風景写真家でもあります。大使として赴任してからも、カメラのレンズを通して、中国の美しい風景を数多く切り取ってきました。
私が足しげく通う撮影スポットの一つに、北京植物園があります。北京市北西部に広がる広大な敷地を擁する北京植物園を訪れる度に、四季折々の自然の美しさを感じることができます。とりわけ、梅、桃、海棠、チューリップなどが咲き誇る春の美しさは、安直な言葉では表現しきれないほどであります。その北京植物園の北東側の静かな一画に、数奇な運命をたどった梁啓超が家族と共に眠っています。
梁啓超は、私から説明するまでもなく、清末・民初に活躍した、中国近代史を代表する思想家・政治家・ジャーナリストであります。1895年、当時22歳の梁啓超は、師と仰ぐ康有為と共に科挙の試験を受けるため上京した際、日清戦争の敗北により締結した下関条約の内容を知って憤慨します。
日本の明治維新にならった政治体制の変革・近代化が必要であると強く認識した彼らは、光緒帝の下で立憲君主制の樹立を目指し、1898年に「戊戌の変法」と呼ばれる改革を推進しました。
しかしながら、その後、西太后・袁世凱らによるクーデター、いわゆる「戊戌の政変」により、100日余りで改革はつぶされ、梁啓超ら「変法派」は弾圧されました。この政変により、仲間の多くが刑死する中、梁啓超は日本に亡命し、その後、辛亥革命の翌年に当たる1912年まで、つまり25歳から39歳までの14年間を日本で過ごしました。ちなみに、同志の康有為もまた、香港経由で日本に亡命しています。
さて、日本滞在中、梁啓超は、「清議報」、「新民叢報」といった雑誌や新聞を創刊するなど、様々な媒体を通じ、日本語に翻訳された西洋の新しい思想や文化を中国国内にもたらしました。彼は、思想面での変遷が指摘されることはありますが、中国の近代における国民思想の確立に果たしたその歴史的役割は大きく、また、近代中国最大のジャーナリストとして、当時の青年知識人に与えた影響は絶大であったと言えるでしょう。
ではなぜ、そのような啓蒙活動が円滑に実現できたのでしょうか。それは、当時梁啓超が、日本で創られた新たな漢字、いわゆる「和製漢語」を積極的に受容し、使用したからであります。当時の日本では、明治維新を経て、西洋文明を積極的に吸収する中で、漢字を新たに組み合わせることにより、西洋の概念を的確に翻訳し、多くの新たな単語が産み出されていました。
つまり、約1,600年前に中国から日本に伝来した漢字は、近代化の中で「和製漢語」として独特の発展を遂げたということであります。そして、梁啓超が西洋の新しい思想を中国に紹介していく過程において、その「和製漢語」は中国に「逆輸入」されることになりました。梁啓超だけではありません。清末の中国は、1905年に科挙が廃止されたことも相まって、空前の日本留学ブームが到来し、中国人留学生の数は、年間2万人にも上ったとされています。
そうした梁啓超や中国人留学生らの活動により中国にもたらされた語彙として、例えば、「世界」、「社会」、「経済」、「科学」、「革命」、「共産党」、「社会主義」、「幹部」、「独立」、「平等」、「自由」、「民主」など、枚挙にいとまがありません。現代中国語の中で、社会科学関連語彙の約7割が「和製漢語」であると言われていますが、そのお陰で、現在、日中間の意思疎通が極めて円滑になっていることは言うまでもありません。この二日間の議論でも、こうした用語が日中双方の有識者の間で幾度も使用されたことでしょう。
かつて中国から学んだ漢字を使い、日本は、その後の政治、経済、科学、文化、思想等、あらゆる面で国を発展させてきました。そして、近代に入り、今度は日本で創られた「和製漢語」で、日本が中国の近代化に寄与することになる、こうした漢字をめぐる日中関係の歴史は、まさに助け合いや学び合い、中国語で言えば「守望相助」の歴史の象徴であります。そうした意味では、梁啓超は、その歴史の過程において極めて重要な役割を果たしたとも言えるでしょう。
本年6月、私は、青島を訪れました。ある日、洋館が並ぶ静寂な坂道を散歩していると、康有為が晩年を過ごした旧居を偶然に見つけました。康有為は、日本滞在中に歳の離れた日本人女性を見初め、4人目の妻としました。二人が青島で共に暮らしたのは数年でしたが、私は、康有為の旧居の窓から青島の青い海を見ながら、その同志・梁啓超に思いを馳せ、そして、漢字が取り持つ不思議な日中両国の「縁」について静かに感じ入りました。
こうした「守望相助」(助け合い)の歴史は、漢字にまつわるものだけに留まりません。これまで日中間では、たくさんの助け合いのドラマが織りなされ、日中関係の歴史を形作ってきました。
日中両国は、引っ越しのできない隣国であり、いわば「永遠の隣人」であります。国交正常化50周年がまもなく終わろうとしていますが、我々はこの機会に今一度、日中関係は世界でもまれに見る「守望相助」(助け合い)の、二国間関係の歴史であることに目を向ける必要があるのではないでしょうか。
最後になりますが、御在席の皆様方の御健勝及び日中関係の更なる発展を祈念するとともに、今次フォーラムの開催に関わられた関係者の御尽力に改めて敬意を表し、私の挨拶とさせていただきます。
御清聴、ありがとうございました。
