「第19回東京-北京フォーラム」における大使挨拶(2023年10月20日)
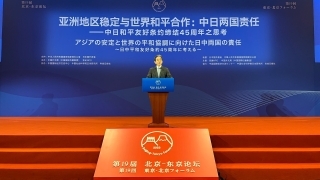

10月19-20日、言論NPOと中国外文局が主催する「第19回東京-北京フォーラム」が北京で対面形式で開催され、「アジアの安定と世界の平和協調に向けた日中両国の責任~日中平和友好条約 45周年に考える~」をメインテーマに、両国の政府関係者や有識者の間で活発な議論が行われました。
垂秀夫在中国日本国大使は、10月20日の全体会議において挨拶を行ったところ、挨拶全文は以下のとおりです。
杜占元・外文局局長、
武藤敏郎・元東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会事務総長、
ご列席の皆様、おはようございます。
第19回「東京-北京フォーラム」が成功裏に開催されましたことを心よりお喜び申し上げます。
今回の「東京―北京フォーラム」は、2019年10月以来、4年ぶりの対面開催であります。新型コロナウイルスの流行や中国の厳しい防疫措置の影響で、日中間の交流が容易でなかった時期もありました。その間も、オンライン等でこの枠組みを維持されてきた関係者の方々の熱意と努力に敬意を表したいと思います。
本年は日中平和友好条約締結45周年です。昨年の日中国交正常化50周年と合わせ、日中関係の来し方を振り返り、未来の日中関係を考える上で、またとない機会であります。
しかし、現下の日中関係に目をやれば、決して楽観視できるものではありません。新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵攻、そして最近の中東情勢等、世界情勢の激変に加え、日中両国の国民感情の更なる悪化が「建設的かつ安定的な日中関係」を構築するための道のりを困難なものにしています。
最近では、福島第一原発のALPS処理水の海洋放出をめぐって日中両国が対立する問題が生じています。ALPS処理水の安全性については、我が国は中国を含む国際社会に対し丁寧な説明を行ってきましたが、中国は、日本産水産物の全面禁輸に踏み切りました。また、中国全土から日本国内に対し嫌がらせ電話が相次ぐ等心ない行為が多々見られました。我が大使館にも、今でも毎日約一万五千件の嫌がらせ電話がかかってきています。
本年も残すところ2ヶ月となりました。日中両国は、日中韓三カ国の枠組みや、11月のAPEC等の国際会議の場を活用しつつ、首脳間を含むあらゆるレベルで意思疎通を重ねることで、政治的相互信頼を回復し、具体的な問題の解決に繋げていく必要があります。
御列席の皆様、
本日は、せっかくの機会ですので、こうした現状を踏まえ、今後の日中関係を前に進めるための手がかりについて、私なりの考えを申し上げたいと思います。
キーワードは「理性を取り戻す」であります。
ご記憶の方も多いかと思いますが、2012年10月、尖閣諸島をめぐって日中両国の世論が激化しました。当時、私は政務公使としてここ北京で勤務していました。中国では、各地の日本の関連施設に対する暴力行為、破壊行為が発生しました。
こうした中、ある中国人有識者が、インターネット上で、中国国民に対し理性的な態度をとるよう呼びかけました。この方は、尖閣諸島に関する日本の立場は決して受け入れられないとした上で、その表現方法として暴力的な行為をとることを譴責したのでありました。当時の社会の雰囲気の中で、こうした立場を表明することは非常に勇気のいることであったでしょう。その後、私は縁あってこの方とお会いする機会を得ました。
お会いしてみると、この方は物事を常に理性的に考えられる方であることはすぐに分かりましたが、同時に、日本、特に歴史問題については、非常に厳しい見方をされていました。どうもその方の父親がかつて旧日本軍と戦った世代であり、その方は物心のついた頃から日本人が如何に残虐非道であるかを何度も聞いて育ってきたとのことでした。
訪日経験があるかと聞くと、「一度もない」とのこと。私は、「日本を批判するのは全くかまわない。ただ、自分の目で日本を見てから批判しても遅くはないのではないか」と述べ、実際に日本を見てみることを勧めました。
その後、訪日を終えたその方に再会しました。その方は私に「たくさん話したいことがあるが、まずは日本滞在中に最も印象に残ったことをお話ししたい」として、ある日本人ボランティアとの出会いについて熱っぽく語り出しました。
その方が日本のある地方都市を訪れた際、その日本人ボランティアは現地ガイドを務めてくれたそうです。英語でのやり取りの中で、尖閣問題についても議論になったとのことでした。
日本人ボランティアは、「尖閣諸島は日本のものであると信じているが、中国にも別の立場があることは承知している。もし本件が国際司法裁判所に付託されたとしても、日本が勝つことになると信じている。ただ、万一、日本に不利な判決が出されたとしても、多くの日本国民はその判決を受け入れるであろう」と述べたそうであります。
これを聞いて、その方は、大きな衝撃を受けたと私に言いました。日本人、しかも一般の市民が、法の支配、ましてや国際司法に対し、とても理性的であり、かつ、高い敬意を抱いていることについて驚愕したとのことでした。その後、その方は、日本行きを出発直前まで反対していた父親に架電し、「私が日本で出会った日本人は、父さんが語っていた戦争中の日本人と全く違っていた。」と直接伝えたそうであります。
日本滞在を通して、その方の対日観は大きく変わりました。それは理性をもって自らの目で日本を見て、自らの頭で考えた結果であります。
あれから十余年、日本を訪れる中国人は飛躍的に増えました。ありがたいことに、実際に日本を訪れた中国人の多くは、日本に対する理解を格段に深めています。こうした方々は、問題があっても理性的な態度で向き合おうとされている方々であります。
もちろん、日本人の側の対中理解の不足や理性の欠いた対中批判といった指摘もあろうかと思います。日中両国間で揺るぎない相互理解・相互信頼を構築していくためには、日中両国の国民・人民が、等身大の相手の姿を理性をもって直視し、そこから虚心坦懐に学ぼうとする姿勢が強く求められています。
私は、このような理性ある方々にこそ、日中関係の未来を託したいと考えます。率直に申し上げて、日中両国においてこうした理性ある人々を増やしていくことは、あるいは砂漠の中で苗木に水をやるような地道で苦しい作業であるかもしれません。それでも、日中関係という土壌に、「理性」という養分を染み渡らせることこそが、我々の目指す「安定的かつ建設的な日中関係」という大木を成育させるための王道であると、私は確信しています。
先日、私は、国慶節の休暇を利用して、福建省の霞浦(赤岸)を訪れました。霞浦は風光明媚な漁村であり、撮影家の聖地として知られていますが、同時に、1200年以上も前に遣唐使船に乗船し、途中で嵐に遭遇した空海が漂着した地でもあります。当初海賊の到来と疑われ、五十日間も上陸が許されませんでしたが、空海が書いた嘆願書を読んだ唐の官吏は理性的に遣唐使一行を接遇し、長安行きを許可することになります。
彼の地において、海から昇る美しい日の出を撮影しながら、空海が上陸した当時の情景に思いを馳せました。日中両国が引っ越しのできない「永遠の隣人」であり、日中両国が世界でもまれにみる悠久の「助け合い」の歴史を持つ関係であることに改めて思いを致した次第であります。
本日この場に集った皆様とこの思いを共有し、数多くの先人達の業績を引き継ぎ、未来に繋げていく覚悟を新たにできればと思います。
最後になりますが、御列席の皆様方の御健勝及び日中関係の更なる発展を祈念するとともに、今次フォーラムの開催に関わられた関係者の御尽力に改めて敬意を表し、私の挨拶とさせていただきます。
御清聴、ありがとうございました。
