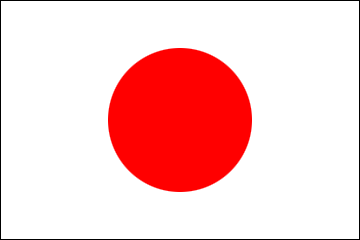中国独占禁止法の改正について
令和6年1月12日
森・濱田松本法律事務所
(令和5年度受託法律事務所)
(令和5年度受託法律事務所)
2008年8月1日から施行された中国[1]の独占禁止法(以下「旧法」という)は、2020年から2回の改正草案の意見募集を経て、2022年6月24日に改正され、2022年8月1日から施行されました(以下「改正法」という)。この改正では、旧法の施行から約14年間の法執行や司法実務、社会情勢の変化を踏まえ、特に、事業者集中の審査手続や独占合意に関する法規制の改正、及び行政処罰の強化等の重大な修正が加えられました。また、この改正に伴い、2023年において独占禁止法に関する一部の下位法令も改正され、またガイドラインも制定されています。独占禁止法は域外適用が可能であるという特徴を有しているため、中国国外の企業においても状況に応じて対応を検討する必要がある点に注意が必要です。
本資料では、改正された独占禁止法とそれに伴って改正された下位法令等の概要及び実務上頻出する論点についてQ&A方式により説明します。
※本資料で引用する条文番号は別途記載されていない限り、独占禁止法の改正法の条文番号を意味します。
※本資料は2023年11月末日時点の情報を前提にしています。
I 改正法の概要
Q1 独占禁止法の改正のポイント
今回の独占禁止法の改正のポイントは何でしょうか。
A1
今回の独占禁止法の改正については、以下の4つのポイントがあると考えています。
1. 事業者集中の審査手続に関する改正
事業者が合併、持分又は資産の買収、合弁等の結合取引による市場競争の排除又は制限効果を防止するため、企業結合取引(事業者集中)に対する事前申告による審査手続が要求される場合があります。改正法においては、この事業者集中の審査手続に関して、審査期間の不算入制度(Stop the Clock)が導入されました。これにより、中国が関係するグローバルM&Aの取引全体のスケジュールに影響を与える可能性もあります。詳細はQ2、Q3、Q4及びQ5をご参照ください。
2. 独占合意に関する法規制の改正
中国の独占禁止法は、商品の再販売価格の固定や再販売最低価格の限定等の、いわゆる垂直的独占行為を禁止しています。旧法においては、垂直的独占行為に関するセーフハーバー制度は規定されておりませんでしたが、改正法においてセーフハーバー制度が規定されることになり、事業者にとって垂直的独占合意が問題になり得る事案についてリスクの予見可能性が高まったと評価できます。詳細はQ6、Q7及びQ8をご参照ください。
3. 行政処罰の強化
改正法では、違反行為に対する過料の金額が大幅に引き上げられ、責任者個人の責任追及に関する規定も追加されるなど、独占禁止法に違反した場合の行政処罰が強化されています。詳細はQ11をご参照ください。
4. 下位規則の整備
中国の独占禁止法では、重要な事項が、複数の独占禁止法の下位規則によって定められていることがあります(例えば、事業者集中の申告基準やセーフハーバー制度などが挙げられます)。改正法の制定に当たり、一部の下位規則はすでに改正されましたが、改正草案のまま正式に制定されていない規則もあります(「事業者集中の申告基準に関する規定」等)。下位規則の今後の改正状況について引き続き注視する必要があります。詳細はQ12をご参照ください。
II 事業者集中の審査手続に関する改正
Q2 事業者集中の審査期間
事業者集中の審査期間については独占禁止法上どのように決められているでしょうか。その期間が中断等されることはあるのでしょうか。
A2
旧法では、事業者集中の通常手続における審査期間は、正式受理・立件されてから最長で合計180日とされています(旧法25条、26条)。ただ、実務上、比較的複雑な案件に関して、審査期間が180日を超過することを避けるために、独禁当局が事業者に対していったん申告を撤回させ、再度申告を提出するよう要求する場合が少なくありません。
改正法では、審査期間不算入制度(Stop the Clock)が新たに設けられ、独禁当局が事業者集中の審査を行う際、下記の事由のいずれかがあるときは、事業者集中の審査期間の中断を決定することができます(32条)。
- 事業者が規定どおりに資料等を提出しておらず、審査業務を進めることができなくなったとき
- 事業者集中の審査に重大な影響を及ぼす新たな状況や事実が発生し、確認を経なければ審査業務を進めることができないとき
- 事業者集中に付加する制限条件についてさらなる評価が必要であり、かつ事業者が中断の請求をしたとき
Q3 事業者集中の申告基準
事業者集中の申告基準はどのように設定されているでしょうか。その基準は引き上げられていますでしょうか。
A3
旧法では、具体的な事業者集中の申告基準を定めておらず、その申告基準を制定する権限を国務院に委ねていました(旧法21条)。この点について、「事業者集中の申告基準に関する規定」では、具体的な申告基準が定められており、下表の「現行申告基準規定」の列に記載された4つの項目のうち、(1)の基準を両方満たすか、(2)の基準を両方満たす場合に、事業者は、事前に独禁当局に申告しなければならないとされています。
改正法においても、申告基準を制定する権限を国務院に委ねている点については変わっていません(26条1項)。ただ、2022年6月27日に公表された「事業者集中の申告基準に関する規定」の意見募集稿(以下「申告基準意見募集稿」という)では、現行の申告基準の売上金額を大幅に引き上げる方向での改正が検討されています。現行の申告基準及び意見募集稿の申告基準は、下表のとおりです。
| 基準 | 項目 | 現行申告基準規定3条 | 申告基準意見募集稿3条 |
| (1) | 集中に参加する全ての事業者の前会計年度の全世界における売上高の合計 | 100億人民元を超える | 120億人民元を超える |
| かつ、そのうち少なくとも2つの事業者の前会計年度の中国国内における売上高 | いずれも4億人民元を超える | いずれも8億人民元を超える | |
| (2) | 集中に参加する全ての事業者の前会計年度の中国国内における売上高の合計 | 20億人民元を超える | 40億人民元を超える |
| かつ、そのうち少なくとも2つの事業者の前会計年度の中国国内における売上高 | いずれも4億人民元を超える | いずれも8億人民元を超える |
他方で、申告基準意見募集稿4条では、上記の申告基準に達しないものの、以下の2つの要件を同時に満たした場合においても、事前に独禁当局に申告しなければならないという新たな基準を設けることも検討されています。
- 事業者集中に参加する1つの事業者の前会計年度の中国国内における売上高が1,000億人民元を超えること。
- 他方の合併当事者又は対象会社の市価(又は評価額)が8億人民元を下回らず、かつ前会計年度の中国国内における売上高がその全世界における売上高に占める割合が1月3日を超えること。
また、改正法においては、事業者集中が国務院の規定する申告基準には達していないものの、かかる事業者集中が競争を排除しもしくは制限する効果を有し又は有する可能性があることを証明する証拠がある場合、独禁当局は、事業者に対し申告をするよう要求することができるとの規定が置かれました(26条2項)。このため、上記申告基準にかかわらず、申告を求められる可能性があることに注意が必要です。
Q4 事業者集中の審査当局
事業者集中の審査は、国家独占禁止局ではなく、地方の独占禁止局で行うことが可能になるようですが、どのような制度でしょうか。
A4
改正法において事業者集中の類別級別審査制度が追加されました。当該制度を踏まえて、国家市場監督管理総局は、2022年8月1日から2025年7月31日までの間、北京、上海、広東、重慶、陝西等の5つの省(及び直轄市)の市場監督管理部門(以下「試行省級市場監督管理部門」と総称する)に一部の事業者集中事件の独占禁止審査を試行的に委託しています。
試行期間中、国家市場監督管理総局は、業務の需要に基づき、以下の基準のいずれかを満たす、一部の事業者集中簡易手続適用事件を試行省級市場監督管理部門に委託して審査を担当させています。
- 少なくとも1名の申告者の住所地が、当該部門が連絡を委託されている関連区域(以下「関連区域」という)にあるとき
- 事業者が持分、資産の買収又は契約等のその他の方式により他の事業者の支配権を取得し、他の事業者の住所地が関連区域にあるとき
- 事業者が合弁企業を新設し、合弁企業の住所地が関連区域にあるとき
- 事業者集中の関連地域市場が区域的市場であり[2]、かつ当該関連地域市場の全部又は主要な部分が関連区域に位置するとき
- 市場監督管理総局が委託するその他の事件
試行省級市場監督管理部門及び関連区域
| 番号 | 試行単位 | 関連区域 |
|
|
北京市市場監督管理局 | 北京、天津、河北、山西、内モンゴル、遼寧、吉林、黒龍江 |
|
|
上海市市場監督管理局 | 上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東 |
|
|
広東省市場監督管理局 | 広東、広西、海南 |
|
|
重慶市市場監督管理局 | 河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南、西藏 |
|
|
陝西省市場監督管理局 | 陜西、甘粛、青海、寧夏、新疆 |
現時点では、各試行省級市場監督管理部門による運用は、すでに開始されており、複数のクリアランス事例が出されています。
Q5 事業者集中のコンプライアンスに関するガイドライン
事業者集中にかかるコンプライアンスについてのガイドラインはあるでしょうか。どのような内容でしょうか。
A5
2023年9月5日、国家市場監督管理総局は、「事業者集中独占禁止コンプライアンス手引」を公表しました。同手引は、6章35条からなり、事業者集中審査制度、コンプライアンスのリスク及びその管理等について包括的に説明するガイドラインとなっています。
この手引は、事業者集中コンプライアンスに関する一般的な指針を提供するものであり、法的強制力はないものの、企業が事業者集中に関するコンプライアンスを遵守するための実用的なガイドラインとなります。
特に、(1)事例を通じて、持分比率が支配権を判断する際の唯一の基準[3]ではない点、(2)取引を段階的に実施する場合の申告時点等の問題点について、第一段階の取引を実行する前に事業者集中申告を行う必要があると明確に指針を示している点、及び(3)事業者集中独占禁止コンプライアンス制度が行政処罰の減免の考慮要素の一つとなることを明らかにした点が、注目に値します。
III 独占合意及び市場支配的地位の濫用に関する法規制の改正
Q6 垂直的独占合意の認定
垂直的独占合意の認定について、規制の対象外であると主張できる場面が規定されたとのことですが、どのように改正されたのでしょうか。
A6
中国の独占禁止法では、禁止される垂直的独占合意の類型として、(1)事業者と取引相手との間における、第三者に対する商品の再販売価格の固定(18条1項1号)、(2)事業者と取引相手との間における、第三者に対する商品の再販売最低価格の限定(18条1項2号)及び(3)独禁当局が認定するその他の独占合意(18条1項3号)を挙げています。
改正法は、上記(1)及び(2)の垂直的独占合意に関して、当該独占合意が競争を排除し又は制限する効果を有しないことを事業者が証明することができる場合は、当該独占合意を禁止しないと規定しました(18条2項)。
垂直的独占合意の認定に関しては、現在の実務上、(1)法律上に規定された適用除外の状況に該当しない限り、原則として当然違法となると判断する考え方と、(2)合意に基づく競争促進効果と競争制限効果を比較したうえで、競争促進効果が競争制限効果を上回る場合には適法となるとして違法性の有無を認定する考え方(合理の原則)が対立しています[4]。
上記規定により、上記(1)及び上記(2)の独占合意については、独禁当局は実務上当然違法を推定するものの、当事者には競争排除又は制限効果を有しないことを自ら証明するチャンスが与えられ、それを証明できた場合は、独占合意と認定されないことになりますので、上記(1)及び(2)を折衷した考え方に近い認定基準が適用されるようになると解されます。これに対し、上記(3)の独占合意については、独禁当局は競争排除又は制限効果を証明する必要があると解されます。
Q7 セーフハーバー制度
旧法では、セーフハーバー制度がありませんでしたが、今回の改正でどのような制度を導入しているのでしょうか。
A7
改正法は、新たに垂直的独占合意に関して「セーフハーバー制度」を導入しました。すなわち、事業者において、(1)その関連市場における市場占有率が一定の基準を下回り、かつ(2)独禁当局の定めるその他の条件に合致することを証明することができる場合は、合意を禁止しないとしています(18条3項)[5]。
また、2023年4月15日に改正・施行された「独占合意禁止規定」では、「事業者と取引相手が合意を形成したとしても、合意に参加した事業者の関連市場における市場占有率が市場監督管理総局の定める基準を下回り、かつ市場監督管理総局が定めるその他の条件に合致することを事業者が証明することができるときは、禁止しない。」と規定されています(「独占合意禁止規定」17条)[6]。
このようなセーフハーバー制度の導入により、事業者にとって独占禁止法違反の判断に対する予測可能性が高くなるといえます。他方で、セーフハーバー制度における市場占有率の基準の適用要件を充足することについての挙証責任は事業者が負うことになっているため、今後は、事業者が関連市場の画定や市場占有率について正確に判断することの重要性がより一層高まるものと考えられます。また、セーフハーバー制度における市場占有率の基準は依然不明確であるため、今後の市場監督管理総局の動向に注視が必要です。
Q8 ハブアンドスポーク型合意
独占合意の形成に関する手配又は幇助行為は独占禁止法の規制対象となるでしょうか。
A8
改正法では、「事業者は、他の事業者による独占合意の形成を手配し又は他の事業者による独占合意の形成のために実質的な幇助をしてはならない。」という条文が新設されました(19条)。さらに、このような幇助をした事業者に、違法な独占合意に対する罰則が適用されることも明記されました(56条2項)。これらの条項は、ハブとなる仲介者を介して各事業者の間で合意がなされる、いわゆる「ハブアンドスポーク型合意」を主要な規制対象としていると考えられています。
独占合意禁止規定18条では、「手配」及び「実質的な幇助」の具体的な内容が示されています。すなわち、「手配」には、(1)事業者が独占合意の当事者ではないものの、合意形成又は実施の過程において合意の主体範囲、主たる内容、履行条件等について決定的又は主導的な役割を果たす状況又は(2)事業者が複数の取引相手と合意を締結し、故意に、自らを通じて競争関係を有する取引相手間で意思の連絡又は情報交換を行わせて水平的独占合意を形成させる状況等が含まれるとされています。また、「実質的な幇助」には、必要な支援の提供、重要な便利条件の創出、又はその他の重要な幇助が含まれるとされています。事業者は、競争者又は取引相手等との連絡等の際、こうした独占合意形成の手配又は実質的な幇助の提供を行わないように留意する必要があります。
Q9 プラットフォーム事業者に対する規制
近年、中国では、プラットフォーム事業者に対する独禁法違反の取締りが強化していいますが、どのような法改正がなされているでしょうか。
A9
改正法では、事業者が、データ及びアルゴリズム、技術、資本の優位性及びプラットフォーム規則等を利用して独占行為又は支配的地位の濫用行為に従事してはならない(9条、22条2項)という規定が加えられ、プラットフォーム経済分野に関する独占禁止の監督管理が強調されるとともに、プラットフォーム経済分野の独占禁止規制が、初めて法律レベルの条文として規定されました[7]。
下位規則レベルでは、「独占合意禁止規定」15条で、事業者が、データ、アルゴリズム、技術及びプラットフォーム規則等を利用して、仕入れて販売する商品価格の統一、限定又は自動設定等の方式を通じて取引相手と商品価格に関する独占合意を形成することを禁止する旨が明記されました。
なお、2023年4月15日に改正・施行された「市場支配的地位濫用行為の禁止に関する規定」21条では、市場における支配的地位を有する事業者が、データ及びアルゴリズム、技術並びにプラットフォーム規則等を利用して、市場における支配的地位を濫用する行為に従事してはならないとされています。また、プラットフォーム事業者の市場支配的地位の認定の際の考慮要素として、取引金額、取引数量、取引量をコントロールする能力が追加されています(同規定12条)。
Q10 知的財産権の濫用に関する改正
知的財産権の保護と独占禁止の規制のバランスをとる必要がありますが、今回の改正では、知的財産権の濫用による競争の排除・制限行為をどのように規制しているのでしょうか。
A10
改正法には、知的財産権の濫用による競争の排除又は制限行為に関する改正に関する改正点はありません。
他方、2015年に制定され、2020年に改正された「知的財産権の濫用による競争の排除又は制限行為の禁止に関する規定」が、今般の独占禁止法の改正を受け、2023年8月1日に再度改正されました。今回の改正では、知的財産権分野における価格関連独占行為に関する規定内容が新たに明記されたほか、知的財産権に関わる事業者集中の申告、申告に対する審査における考慮要素及び制限的条件付きのクリアランスの条件内容等について、今回の改正で新たに規定されました。また、パテントプール[8]に関して、正当な理由なく、特許の使用範囲を制限することや、特許の有効性に疑義を呈することを禁止すること、特許の抱き合わせ許諾等の行為を実施することを、市場支配的地位の濫用行為に該当するとして禁止するとともに、事業者は正当な理由なく、知的財産権行使の過程において、標準の制定及び実施を利用して、特定事業者が標準制定に参加することを排除する等の独占合意を達成してはならないと明確に規定しました。加えて、標準必須特許の権利者が差止命令による救済を濫用する問題について規定[9]を追加し、標準必須特許権者に対して合理的な範囲内で差止命令による救済の権利を行使すべきであることを要求し、かつ「善意の交渉」を前提条件として規定しました。
上記のほか、国家市場監督管理総局は、2023年6月30日から2023年7月29日までの間、「標準必須特許分野に関する独占禁止指針(意見募集稿)」の意見募集を行いました。この意見募集稿においては、標準必須特許に係る行為が競争を排除し又は制限するか否かを分析するための基本原則[10]が明確にされ、標準必須特許に関わる独占合意、市場支配的地位の濫用及び事業者集中等の行為を規制する内容が盛り込まれています。また、標準の制定・改正に参加する特許権者又は特許出願人が、標準の制定・改正のいずれの段階においても標準必須特許に関する情報を開示しなければならないこと、標準必須特許権者と標準実施者との間で標準必須特許に係るライセンスの料率、数量、期限等のライセンス条件に関して誠実な交渉を行わなければならないこと等の内容も含まれています。ただし、本資料の脱稿時点で、同指針は正式に制定されていないため、今後の立法活動及び実務における動向を引き続き注視する必要があります。
IV 行政処罰の強化
Q11 罰則の強化
今回の法改正で各独占禁止法の違反行為に対する行政処罰はどのように厳格になっているでしょうか。
A11
改正法は、独占禁止法の規定に違反した独占合意及び事業者集中の実施等の違法行為に対して、下表のとおり、旧法から処罰金額を引き上げ、また個人が責任を負うべき場合を拡大して、違法行為の代償を大幅に上昇させました。特に、事業者集中の手続に違反した場合、旧法では競争制限効果がある場合であっても、50万元以下の過料にとどまっており、事業者集中手続を懈怠してしまったとしても処罰内容自体は必ずしも重大ではありませんでした。しかし、今後は売上高の10%という過料に処される可能性があります。このように、売上高を基準とする過料は高額となる可能性もあるため注意が必要です。
| 行為 | 具体的な違法行為 /責任主体 |
処罰(旧法) | 処罰(改正法) |
| 独占合意 | 独占合意を形成し、かつ実施した場合 | 違法所得の没収、前年度販売額の1%以上10%以下の過料 (旧法46条) |
旧法の規定に加えて、前年度売上高がない場合、500万元以下の過料に処する規定を追加 (56条) |
| 形成した独占合意を実施していない場合 | 50万元以下の過料 (旧法46条) |
300万元以下の過料 (56条) |
|
| 事業者の法定代表者、主要責任者及び直接責任者が独占合意の形成につき個人責任を負う場合 | 該当規定なし | 100万元以下の過料 (56条) |
|
| 独占禁止法の規定に違反して実施された事業者集中 | 競争を排除し、もしくは制限する効果を有し、又はこれらの効果を有する可能性がある場合 | 50万元以下の過料(旧法48条) | 前年度売上高の10%以下の過料 (58条) |
| 競争を排除し、又は制限する効果を有しない場合[11] | 500万元以下の過料 (58条) |
||
| 独禁当局による調査の拒絶・阻害行為 | 個人に対する処罰 | 2万元以下の過料 情状が重大な場合は2万元以上10万元以下の過料 (旧法52条) |
50万元以下の過料 (62条) |
| 単位に対する処罰 | 20万元以下の過料 情状が重大な場合は20万元以上100万元以下の過料 (旧法52条) |
前年度売上高の1%以下の過料 前年度売上高がない場合、又は売上高の計算が困難な場合、500万元以下の過料 (62条) |
|
| 独占禁止法に違反する行為 | 独占禁止法に違反し、情状が特に重く、影響が特に深刻であり、特に重大な結果をもたらした場合 | 該当規定なし | 独占合意(56条)、市場支配地位の濫用(57条)、事業者集中(58条)及び独禁当局による調査の拒絶・阻害行為(62条)に対する過料金額の2倍以上5倍以下の過料 (63条) |
V 独占禁止法の下位規則等の整備状況・管轄当局
Q12 独占禁止法の法体系
独占禁止法の改正に関して、下位規則等の制定・改正が進められているようですが、現状どのような規則等が制定・改正されようとしているでしょうか。
A12
独占禁止法に関する主な規則及びその改正状況は以下のとおりです。
| No. | 現行の下位規則 | 改正状況 | 改正後の要点 |
|
|
事業者集中審査規定 (国家市場監督管理総局2020年10月20日公布、2022年3月22日改正、2022年5月1日施行) |
2023年3月10日改正、2023年4月15日施行 |
|
|
|
事業者集中の申告基準に関する規定 (国務院2008年8月1日公布、2018年9月18日改正、同日施行) |
2022年6月27日意見募集稿公表(意見募集期間:2022年7月27日) 正式版未公布 |
/ |
|
|
金融業事業者集中申告における営業額の計算規則 (商務部等5部門2009年7月15日公布、2009年8月15日施行) |
修正案の意見募集なし | / |
|
|
事業者集中申告に関する指導意見 (商務部独占禁止局2009年1月5日公布、国家市場監督管理総局2018年9月29日改正、同日施行) |
同上 | / |
|
|
事業者集中簡易事件の申告に関する指導意見 (商務部2014年4月18日公布、国家市場監督管理総局2018年9月29日改正、同日施行) |
同上 | / |
|
|
独占合意の禁止に関する暫定規定 (国家市場監督管理総局2019年6月26日公布、2019年9月1日施行) |
「独占合意の禁止に関する規定」に名称変更 2023年3月10日改正、2023年4月15日施行 |
|
|
|
市場支配的地位濫用行為の禁止に関する暫定規定 (国家市場監督管理総局2019年6月26日公布、2019年9月1日施行) |
「市場支配的地位濫用行為の禁止に関する規定」に名称変更 2023年3月10日改正、2023年4月15日施行 |
|
|
|
知的財産権の濫用による競争の排除又は制限行為の禁止に関する規定 (国家工商行政管理総局2015年4月7日公布、国家市場監督管理総局2020年10月23日改正、同日施行) |
2023年6月25日改正、同年8月1日施行 |
|
|
|
行政権限の濫用による競争の排除又は制限行為の制止に関する暫定規定 (国家市場監督管理総局2019年6月26日公布、2019年9月1日施行) |
「行政権限の濫用による競争の排除又は制限行為の制止に関する規定」に名称変更 2023年3月10日改正、2023年4月15日施行 |
|
|
|
独占行為に起因する民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する規定 (最高人民法院2012年5月3日公布、2020年12月23日改正、2021年1月1日施行) |
2022年11月18日意見募集稿公表(意見募集期間:2022年12月9日) 正式版未公布 |
/ |
Q13 独占禁止法の主管当局の変遷
独占禁止法の主管当局は、どの部門でしょうか。以前は複数の部門に分けて監督管理がなされていましたが、現在はどのような状況でしょうか。
A13
独占禁止法の施行当時、独占禁止法の主管当局は、国家発展改革委員会(価格に関する独禁法違反行為の取締りを担当)、国家工商行政管理総局(価格以外の独禁法違反行為の取締りを担当)及び商務部(事業者集中の審査を担当)という3つの部門に分かれていました。
2018年の国家機関改革により、国家市場監督管理総局が設立されたことで、3つの部門に分かれていた独占禁止法執行機能は、国家市場監督管理総局の下に設置された国家独占禁止局に集約されるようになりました。
さらに、2021年11月18日には、国家独占禁止局が、国家市場監督管理総局の内設の「司局級」の部門から「副部局」に格上げされ、その下に3つの司、すなわち、主に独占禁止制度に関する措置やガイドラインの策定を主導し、独占禁止業務の総合的な調整といった業務を担う「競争政策協調司」、主に独占合意や市場支配的地位の濫用等に関する法執行を担当する「独占禁止執法一司」、及び主に事業者集中の独占禁止審査を担当する「独占禁止執法二司」が設置されました。
本資料の利用についての注意・免責事項
本資料は、森・濱田松本法律事務所が2023年11月末日までに入手した中国の法令等の公開情報に基づき作成しており、その後の法令改正等を反映していません。また、本資料に掲載する情報について、一般的な情報・解釈がこれと同じであることを保証するものではありません。本資料は参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。
日本政府、外務省、在中国日本国大使館、領事館及び森・濱田松本法律事務所は、本資料の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的又は懲罰的損害等について、一切の責任を負いません。
以上
[1] 本資料において、中国とは中国大陸を含み、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾を含みません。
[2] 例えば、地方政府の政策や商品・役務の性質等により一つの省や市に限られる市場を指します。
[3] 事業者が、対象会社の少数持分を取得したとしても、対象会社の年度事業計画、財務予算、高級管理職の任免等の経営管理事項を単独で否決する権利を持つ場合、対象会社に対して(共同の)支配権を取得したと認められ、事業者集中に該当するとされています。実務上、過去に、10%以下の持分しか取得していない取引が、対象会社の支配権を取得したと認定され、事業者集中申告を懈怠したとして処罰を受けた事例も存在します。
[4] 垂直的独占合意の認定に関しては、実務上、人民法院は、(2)の考え方に基づき、合理の原則に基づき事業者が形成した合意の競争排除又は制限効果の有無を詳細に分析したうえ、垂直的独占合意に該当するか否かを認定する場合が多いのに対して、独禁当局は、(1)の当然違法の原則に基づき、事業者と取引相手の間で形成した合意が旧法14条(垂直的独占合意)の規定に合致すると判断した後、15条(独占合意禁止の適用除外)に定める適用除外の状況に該当しない限り、競争排除又は制限効果を有すると推定し、垂直的独占合意が違法であると判断する傾向が見られます。
[5] 2021年の独占禁止法改正の意見募集稿では、セーフハーバー制度は水平的独占合意、垂直的独占合意及び独占合意形成の手配等に適用されるとされていましたが、改正法では、セーフハーバー制度は垂直的独占合意にのみ適用されることとなりました。
[6] なお、上記(1)及び(2)の詳細(垂直的独占合意に関するセーフハーバー制度の適用条件)については、2022年6月27日に公表された「独占合意の禁止に関する暫定規定」の意見募集稿(以下「独占合意禁止規定意見募集稿」という)において、(1)事業者及び取引相手の関連市場における市場占有率が原則として15%を下回ること及び(2)事業者と取引相手間の合意が競争を排除し又は制限することを証明する証拠がないことの双方を事業者が証明できることというように具体化されていましたが(独占合意禁止規定意見募集稿15条1項)、この市場占有率15%以下という従来よりも厳しい基準及びその証明資料を定める当該意見募集稿の内容は「独占合意禁止規定」では採用されませんでした。
[7]「プラットフォーム経済分野における独占禁止に関する指針」には、データ及びアルゴリズム、技術、資本の優位性及びプラットフォーム規則等を利用する独占行為の具体的な態様が列挙されています。
[8] パテントプールとは2以上の事業者が各自の特許をプール構成員又は第三者に共同許諾することをいいます。
[9] 市場支配的地位を有する事業者は、標準必須特許の許諾の過程において、公平、合理、無差別の原則(FRAND)に違反し、善意の交渉を経ることなく、法院又はその他の関連部門に対して関連知的財産権の使用を禁止する判決、裁定又は決定などを請求し、被許諾者に不公平な高額又はその他の不合理な取引条件を受け入れさせてはなりません。
[10] (1)知的財産権の濫用と同一の規制原則を採用し、「独占禁止法」の関連規定に従うこと、(2)知的財産権保護と独占禁止の関係を把握し、知的財産権の保護と市場における公平な競争の促進の両方に配慮すること、(3)標準の制定及び実施過程における必須特許の情報開示、ライセンスに係る約束及びライセンス交渉の法令遵守状況を十分に考慮すること、(4)標準必須特許の革新に係る合理的な見返りを保障し、標準必須特許権者と標準実施者の利益の均衡をより適切にはかること
[11] 改正法は競争を排除し、又は制限する効果の有無によって場合を分けて異なる処罰を規定しており、競争排除又は制限効果がない場合に前年度販売額の一定割合に基づく高額な過料がなされる可能性を排除した。